「廊下」から見るクリニックの内装について

「クリニックの内装」というと、多くの人は、壁や床、間取り、カウンターを初めとする設備を想像します。
ただ、これらはもちろん大切なものではありますが、「廊下」もまた非常に大切なものです。
ここで「クリニックの廊下」に注目して、クリニックの内装デザインについて考えていきましょう。
クリニックの廊下の幅・手すりと建築基準法
クリニックは、一般住宅などとはまったく違った性質を持つものです。そのため、廊下の幅についても、建築法や医療法、そしてバリアフリー法の制限を受けます。
たとえば、「19床以下の病床があるクリニックにおいては、片方居室の場合は1.2メートル以上の、両側居室では1.6メートル以上の幅がなければならない」と定められています。
加えて、「廊下は車いすが簡単に使用できるように、廊下の幅は1.2メートル以上にする、1.8メートル以上にすれば一部(容積率など)で緩和措置が受けられる」などのような決まりがあります。
また、階段においては、「直通階段を必ず設けるようにして、階段の踏む面は24センチ以上としなければならない」「手すりを設けなければならない」とされています。
クリニック作りをするためには、まずはこれらの法律をクリアしなければなりません。
下記の記事では、クリニックの内装に関連する建築基準法や医療法について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
クリニックの内装を考える前に知っておきたい建築基準法と医療法の話
クリニックの床材選び

クリニックの床材選びのポイントは以下の通りです。
滑り防止機能がある素材や、衝撃を吸収できる素材を選ぶ
クリニックの廊下では、車椅子利用者や足腰に不安のある高齢者、小児患者などさまざまな来院者が行き交うことが想定されるため、滑りにくい一方で、歩行や車椅子の車輪の動きを妨げない素材を選ぶことが重要です。
また「万が一転倒してしまった場合でも、けがをしにくい床材を選ぶ」という視点も大切です。衝撃を吸収できるクッション性のある床材を選べば、患者様が転倒しても大事にいたりにくくなるでしょう。
防音機能がある床材がおすすめ
意外に思われるかもしれませんが、クリニックによっては「防音性」「吸音性」がある床材が求められることもあります。
たとえば、「入院設備があり、談話室がある」「リハビリを行う施設を併設している」などのクリニックの場合です。また、大きな音がする医療機器を使うクリニックも、防音・吸音に配慮するとよいでしょう。
なお、防音対策は床材単体ではなく、壁材・天井材・間取りとの組み合わせで検討することが基本です。
ストレッチャーなどを使う可能性がある場合は、耐久性の高いものを
CTやMRI設備があるクリニックでは、ストレッチャーなどを使用する可能性もあることを想定して、耐荷重・耐キャスター性に優れた床材(塩ビ系など)。適切な素材を初期導入することで、将来的な床面損傷や修繕費用の削減にもつながるでしょう。
自院のデザインテーマにあったものを選択する
クリニックの床材選びでは、「安全性」「耐久性」「機能性」が優先されますが、これらを満たした上で「デザイン性」にもこだわることで、来院者に与える印象が大きく変わります。
たとえば、
・薄茶色:落ち着き・安心感
・白系:清潔感・開放感
・ダーク系:高級感・モダンな印象
など、色彩による心理的効果も考慮することで、ブランディングの一貫にもなります。
近年では、機能性とデザイン性を両立させた床材も多く、カラーバリエーションやパターンも豊富です。院内全体のトーン&マナーに合わせて選ぶことで、空間全体の統一感が生まれるでしょう。
クリニックの廊下と導線について
最後に、「クリニックの廊下と導線」について解説していきます。
広めのクリニックでは直線型にすると迷いにくい
体調不良の患者は集中力が低下しやすく、無駄な移動が負担になります。そのため、廊下には「直感的に移動できる設計」が求められます。
広いクリニックでは、「直線型の動線」を採用し、途中に進行方向を示す案内表示(例:←CT室 / ↑リハビリ室)を設置することで、身体的な負担やストレスを減らせます。
回遊型+真ん中に受付スペースはスタッフの利便性が高い
コンパクトな設計のクリニックの場合、回遊型(円形動線)+中央受付方式が有効です。利点としては、スタッフが中央から全体を見渡せるほか、患者からの問合せにも迅速に対応できます。
またこのタイプの廊下の場合、スタッフは受付スペースを使ってショートカットすることができるので、スタッフの移動距離を最小限にすることができます。これにより、スタッフがタイムロスなく動けるようになるため、患者様の待ち時間も減らすことができます。
「色分け」をすると、直観的に導線を把握しやすい
廊下や壁に色分けラインやゾーンごとの床色の違いを取り入れると、動線が直感的に把握しやすくなります。特に小児科や高齢者向けクリニックでは効果的です。
またこの色分けの手法は、上で挙げた「直線型の動線」「回遊型」とも組み合わせることが可能です。
「廊下」からクリニックの内装を考える
廊下は、診察室や待合室などの空間をつなぐ中核的な存在であると同時に、クリニック全体の印象や使い勝手を大きく左右する要素です。
機能性・安全性・デザイン性のバランスをとりながら、適切な素材やレイアウト、動線設計を行うことで、患者にもスタッフにも優しい空間が実現できます。
フルサポクリニックでは、廊下を含めたクリニックの内装設計をトータルにサポートしています。
診療科にあわせた最適なプランをご提案しますので、クリニックの内装をご検討の際には是非ご相談ください。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部










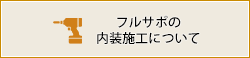

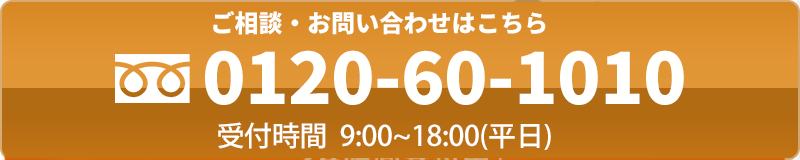
医療、介護施設の設計施工を得意とする「FULLsupport」が運営。
当サイトではクリニックにまつわる設計や内装工事にまつわる記事を随時更新中