小児と成人を同じ診療施設で診察することのメリットと内装の考え方

「小児と成人をどちらも診察する」というクリニックは、決して少なくはありません。
この場合、建物の考え方としては、
・敷地も棟も分ける
・同敷地内だが、棟は分ける
・同敷地内、一つの棟で小児も成人も診る
の3つがあります。
今回はそのなかでも、2番目の、「同敷地内だが、棟は分ける(成人を診察する建物と、子どもを診察する建物を別々に、同じ敷地内に建てる)」を取り上げて、そのメリットや内装デザインのポイントについて解説していきます。
小児と成人で診察する建物を分けるメリット

同じ敷地内に、成人を診る棟と、子どもを診る棟を分けて建てることにはいくつかのメリットがあります。
・子どもに特化した内装デザインにできる
・「子連れの親御さん」が通いやすくなり、家族ぐるみで診ることができる
・予防内科などの案内がしやすい
・駐車場などのスペースを無駄なく確保しやすい
・「どちらを受ければよいか分からない」という患者さんに寄り添える
子どもに特化した内装デザインにできる
クリニックに代表される医療機関は、どうしても子どもにとって「嫌な場所」になりがちです。特に内装が大人向けであったり、暗い雰囲気であったりする場合、不安をより募らせてしまう可能性があります。だからといって、成人も来るクリニックで、子ども向けすぎる内装デザインにしてしまうと、今度は大人の方が落ち着きません。
しかし棟を分けることによって、このようなデメリットを解消することができます。詳しくは後述しますが、小児科の棟にはおもちゃを作りつけた壁を作ったり、階段の段差を低くしたり…というやり方を採用できます。
これによって、「あのクリニックは楽しい」「家では遊べないおもちゃが遊べる」という、子どもにとって通いたくなるクリニックを作ることができます。また大人も落ち着いた雰囲気の棟で診察を待つことができます。
「子連れの親御さん」が通いやすくなり、家族ぐるみで診ることができる
成人用の棟と、子ども用の棟を同じ敷地内で別々に建てることで、子連れの親御さんが通いやすくなるのは大きなメリットです。一家庭を診ることができればそれだけ受け入れられる患者の幅が大きくなるため、経営面で大きなプラスとなります。
また、これ以外に注目したい点として、「親御さんの気持ちに寄り添えること」が挙げられます。
親御さんのなかには、「自分がずっと通っていたところに子どもも連れていきたい」「初めての場所で子どもの泣く声が迷惑になりそうで不安」と考える人もいます。
しかし同じ敷地内でありながら大人向けと子供向けの建物が別になっているクリニックならば、このような心配もなくなります。
予防内科などの案内がしやすい
現在は医療機関は「不調になった場合に、それを治すところ(症状を軽くするところ)」であると同時に、「病気にならないように予防するための措置を取るところ」でもあります。特に歯科医院などはこの傾向が顕著です。
「予防」は、成人だけではなく、子どもに対しても有用です。予防内科・予防歯科をしっかり考えていくことで、大きな健康トラブルも起きにくくなります。
「成人を診る棟でも、子どもを診る棟でも、予防医療のことを案内する」というスタイルをとっていると、子ども用の棟にやってきた親御さんが自身の、また成人用の棟にやってきた親御さんがお子さんの予防医療に対して興味を持つことができます。「子どもの未来のためにも自分が健康でいなければ」「子どもが将来的に苦しまなくてよいように予防しなければ」という考えを、「子ども」を通して親御さんに啓蒙できるのは非常に大きな魅力です。
駐車場などのスペースを無駄なく確保しやすい
成人用のクリニックと子ども用のクリニックを別の場所で開院した場合、駐車場などを複数確保しなければならなくなります。
しかし同じ敷地内に成人用の棟と子ども用の棟を一緒に建てれば、このようなロスが起きなくなります。
また、クリニックへのアプローチも最小限で済むため、土地を無駄なく使うことができます。これは地価が高い都心部などでは特に有効な考え方です。
ただ、「成人も診るし子どもも診るので、駐車場が足りなくなる可能性がある」という場合は、別のところに駐車場を確保したり、予約診療のみとしたり、コインパーキングの補助券を出したりといった工夫が必要になるかもしれません。
「どちらを受ければよいか分からない」という患者さんに寄り添える
基本的に、小児科は15歳以下を対象としています。ただ、親御さんのなかには「現在15歳ではあるが、体がほかの子に比べて小さい」「持病があり、子どもの頃から診てもらっていた耳鼻科がある。15歳になったからといって、すぐに違う病院に変えてもよいのか」と迷う人もいます。また、なかには、「子どもを対象とする耳鼻科に行ったのに、成人の耳鼻科に言ってくれと案内された(またはその逆)」というケースもあります。
これは親御さんにとって、時間的にも手間的にも非常に大きな負担となります。
しかし子ども用と成人用の棟を併設していれば、この案内もスムーズに行えます。
内装のポイント

最後に、内装のポイントについて解説していきます。
【小児科棟】子どもが喜ぶデザインを意識する
子ども用の棟を独立して建てた場合、小児特化のデザインにできます。壁面や床面に線路デザインをプリントしたり、迷路模様になっている絨毯を敷いたりすることができます。
また、子ども用の柵を着けることで、いわゆる「脱走」「飛び出し」も防ぐことができ、スタッフの目も届きやすくなるでしょう。
子どもに合わせて階段の高さを調整したり、手すりを使いやすい高さにしたりできるのもメリットです。
「建物全体がキッズスペース」のようなコンセプトのクリニックを作れるのは、子ども用と成人用の棟を分けることの大きなメリットです。
こちらの記事では、小児科の内装のポイントについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
小児科の内装のポイント!機能面やデザイン面から見た注意点を紹介
【成人対象棟】バリアフリーやリラックスできる空間を意識する
子どもを対象とする棟では、待合室⇔玄関の廊下を狭くするなどの工夫も推奨されますが、成人を対象とする棟の場合は車いすが旋回できるような広めのスペースにするのがよいでしょう。また、トイレなども、車いすが入れるスペースを確保します。
内装デザインは落ち着いたものとし、隣との距離を適切にとれるようにするなどの工夫が求められます。感染症対策という観点から、隣の人との距離が近くなってしまいがちなソファではなく、個人用のチェアを採用してもよいでしょう。
また、大人を対象とするクリニックの場合は「プライバシーの保護」を重要視すべきです。パーテーションではなく扉や防音壁紙などを積極的に採用し、診察の内容が他者に聞かれないように工夫します。
【小児科―成人を対象とする科の連携】
同じ敷地内で子ども用の棟と成人用の棟を建てる場合は、スタッフは渡り廊下などを使って双方の棟にアクセスしやすくすることが重要です。基本的にはこの渡り廊下はスタッフ専用としておくと、運用がしやすいでしょう。
また、スタッフ休憩室を真ん中に置くなどの工夫もおすすめです。
これは高い防音効果を示すとともに、「今忙しいから少し手伝って」「トラブルが起きたから来てください」などのように緊急時の対応にも役立つ方法です。
まとめ
小児と成人、両方を診られるように、同じ敷地内で棟を分けて建物を建てることには数多くのメリットがあります。
「分けるからこそ実現できる内装デザイン」にも注目して、よりよいクリニックを作っていきたいものですね。
フルサポクリニックでは医療モールをはじめ、さまざまな形態のクリニックの内装デザインを手がけています。診療科ごとに棟を分けたい、同じ建物内で複数の診療科を診たいという場合にも最適なプランをご提案いたします。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部










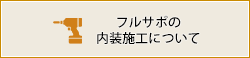

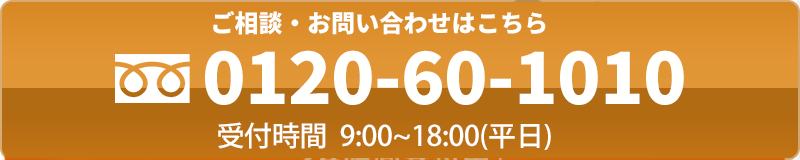
医療、介護施設の設計施工を得意とする「FULLsupport」が運営。
当サイトではクリニックにまつわる設計や内装工事にまつわる記事を随時更新中