あなたのクリニックは大丈夫?クリニックにおけるリフォームを、法律の観点から考える

※撮影用に作られた架空の創作新聞です。記事内容はすべてオリジナルのダミーです。
日本の耐震基準は、時代に応じて徐々に厳しくなっていっています。
そのため、クリニックを新しく建てる際や、リフォームをする場合は、この耐震基準などをしっかり確認する必要があります。
ここでは、法律の面から「クリニックのリフォーム」について解説していきます。
変わる耐震基準法、国への報告義務とは?
まず、「耐震基準の移り変わり」の面から、クリニックのリフォームについて解説していきます。
耐震基準は、改正のたびに厳しくなっている
日本は地震大国として知られていて、たびたび大きな震災に見舞われています。
このような震災による被害をできるだけ小さくするために、震災後には建築基準法の見直しが行われてきました。
建築基準法における耐震基準は1950年に設定され、1971年に改正されています。
建築基準のもっとも大きな改正は、1978年に起きた宮城県沖地震をきっかけとするもので、1981年に行われました。このとき以降に確認申請を受けたものは「新耐震(の基準を満たす建物)」とされていて、それ以前の「旧耐震(の建物)」とは区別されます。
また、1995年の阪神淡路大震災をきっかけに、2000年に再度見直しが行われています。さらに、東日本大震災を受けて、2013年にも法律の改正が行われました。
耐震基準は、見直しが行われるたびにより厳しくなっていっています。今後もこのような流れは変わらないものと思われます。
国への報告義務を確認しておく必要がある
クリニックはその性質上、多くの、しかも心身になんらかの不具合を抱えた人が訪れる場所です。
そのため、一般住宅に比べてより厳しい基準が設けられています。2013年の法改正では、クリニックを含む大規模な建築物かつ不特定多数の人が行き来するところに関しては、耐震診断の実施およびその結果の報告が義務とされるようになりました。
上で「耐震基準法のもっとも大きな改正は、1981年のことである」としました。
先生のなかには、「父の代に建てた建物をそのまま引き継ぎ、クリニックを営んでいる」という人もおられるかもしれません。しかし1981年の5月31日以前に建てられたクリニックに関しては、耐震診断を受けることが義務付けられています。
さらに、耐震診断によって耐震改修が必要と判断されたクリニックにおいては、速やかに改修工事に努めるようにという見解が出されています。
増築リフォームをしたいときに見るべきポイント
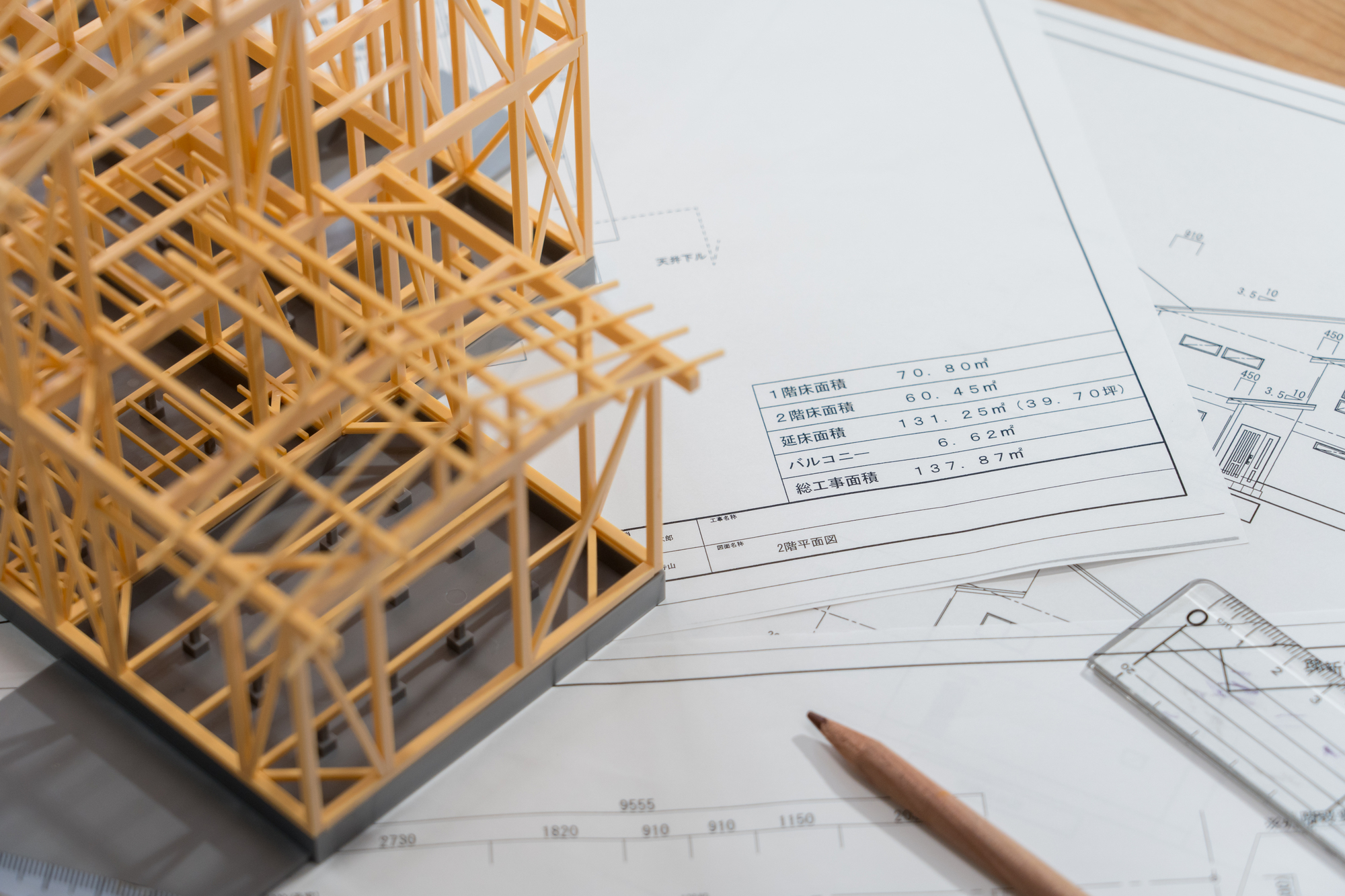
ここからは、「増築・改修リフォームをしたいと考えたときに考慮すべき点」を、法律の面から見ていきましょう。
1981年以前に建てた場合は、補強工事が必須
1981年以前に建てられたクリニックは、改修する際には補強工事を行うことが必須とされています。なお2005年までは「構造的に大きな変化がない程度の工事であれば、増築の真正を認める」と解釈されていましたが、2005年以降はたとえ構造的に影響がない範囲の増築工事であっても、検査・補強なしには増築ができなくなりました。
たとえば、「クリニックが手狭になってきたから、クリニックをより広くするための工事をしたい」などのようになったときには、地震に耐えられるように補強工事を行わなければならなくなったのです。
ちなみに、正しい手順で報告・補強をした場合であっても、1981年以前に建てられたクリニックについては現在の建物の1.5倍までしか拡張できません。
大規模な修繕も確認申請がいる
「増築ができなくても、クリニック内の改修・修繕は問題がないのではないか」と考える人もいるかもしれません。
しかし実は、改修・修繕にも制限が設けられています。小規模な改修・修繕は問題ありませんが、建物の構造に大きな影響を及ぼす部分(床や梁、屋根などを大きく改修する場合は、行政機関に対して確認申請を行う必要があるのです。
クリニックは人の命を預かる場所であること、また行政機関の判断もそれぞれで異なることから、一度相談してみるのが安心です。
場合によってはリフォームが禁止されることもある
さらに、クリニックの建物の状態によっては、リフォーム自体が禁止されている場合もあるので注意が必要です。
たとえば、木造のクリニックで延べ面積が500㎡もしくは建物の高さが13mを超えるものなどは、リフォームすることができないとされています。
このため、「新しくクリニックを開業するにあたり、昔クリニックとして営まれていた建物を利用する」などを目的に物件を購入した場合、リフォームができずに困ってしまうということも起こり得るのです。
クリニックのリフォームで法律の観点から気にすべきその他のポイント
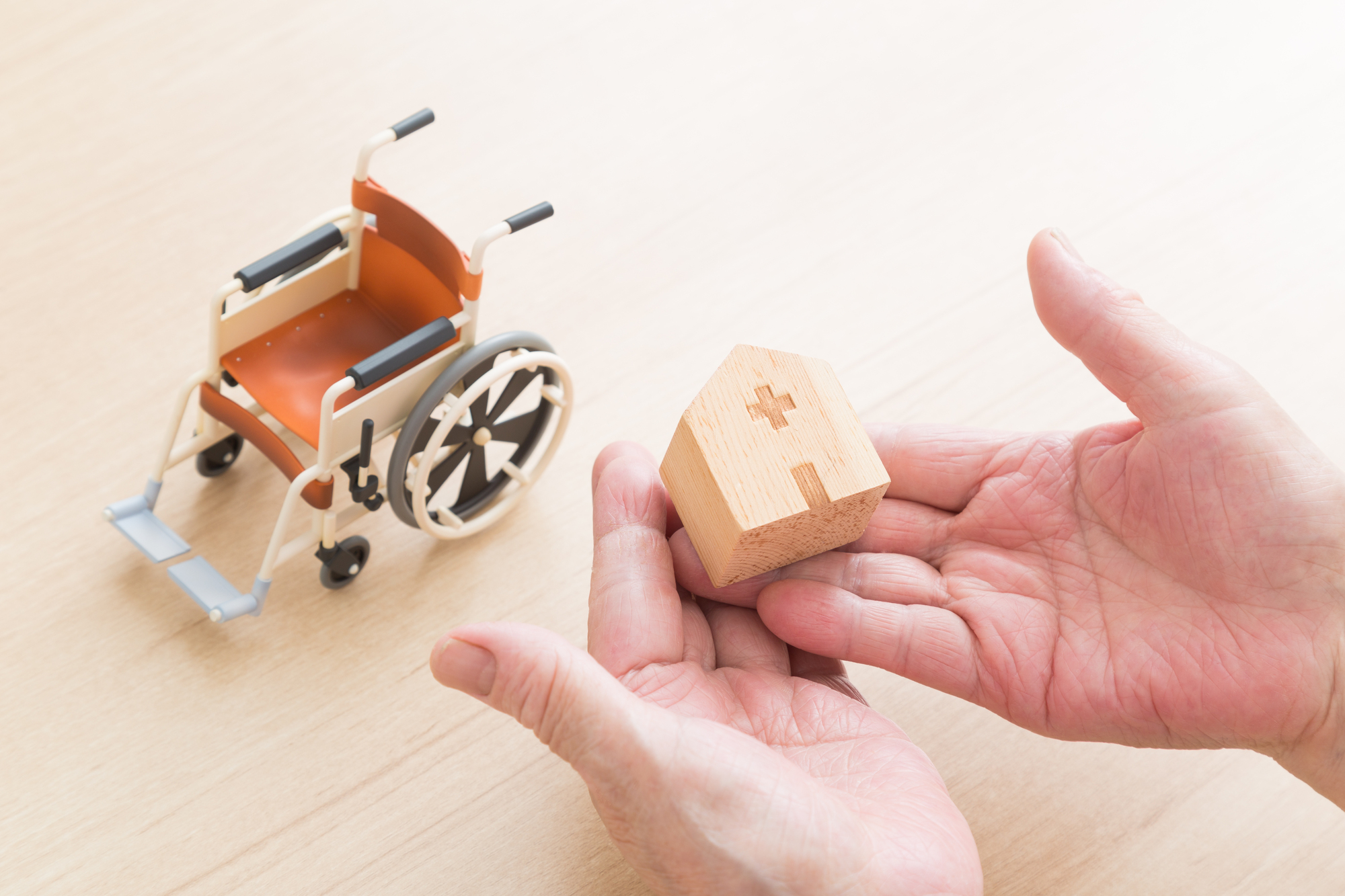
上記では耐震法を基準にクリニックのリフォームについて解説してきましたが、クリニックにはほかにも気にするべき法律があります。
最後に、そのあたりについても触れていきましょう。
努力義務であるものの、医療機関ならば守りたい「バリアフリー法」
バリアフリー法は、障がいを抱えている人や、ご高齢の方、またけがや病気を抱えている人などが行動しやすいようにするために定められた法律です。
たとえば、車いすの患者様同士ですれ違える通路幅を確保したり、出入り口にスロープを設けたり、手すりなどを設置した広いトイレを設置したりといったことが、バリアフリーの例にあたります。また、バリアフリーといえば「段差をなくすこと」だと思われがちですが、座る―立ち上がる などの動作をしやすくするための適切な段差を設けることもバリアフリー化のひとつだといえます。
バリアフリー法をクリアすることはあくまで努力義務に留まっていますが、医療機関であるクリニックでは当然クリアするべきものだといえるでしょう。
「広さ」「階層」によって制限が異なる「消防法」
クリニックの開業・リフォームにおいては、消防法を守ることも重要です。
消防法とは、火災を予防したり、火災が起きたときの被害を減らしたりするために定められた法律をいいます。
クリニックに適用される消防法は、病床数の数によって異なります。
病床数が4床以上のクリニックでは、消化器の設置や自動火災報知設備などの設置が必須です。対して病床数が4床未満のクリニックの場合は、「150㎡以上で、消化器の設置が必要」などのように、広さによって設置の義務の有無が変わってきます。
また、ビルで開業予定・開業しているクリニックの場合は、高いところにあるクリニックであればあるほど、消防法による制限が厳しくなります。
法律から見るリフォーム~なぜクリニックにはこのような規制が掛けられているのかを知る
「クリニックが古くなってきたから」「患者様の数が増えてきたから」という理由で、リフォームを考える先生方は決して少なくありません。
そのときにまず考えなければならないものとして、耐震基準法や消防法、バリアフリー法などの法律があります。
日本は地震大国として知られていますし、医療機関であるクリニックには心身に不調がある患者様が多く訪れます。災害が起きたそのときに、患者様に及ぶ被害を最小限にするために、クリニックはさまざまな対策をとらなければなりません。「いのちを守るための機関」として、どのような義務が課せられているのか、どのような取り組みが必要なのかを考えていきましょう。
私たちフルサポクリニックは、建築基準法・耐震基準に基づいたクリニックの内装リフォームを専門としています。数多くの実績をもとに、各種法規制をクリアした最適なプランをご提案いたします。クリニックのリフォームでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部










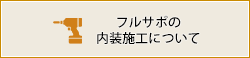

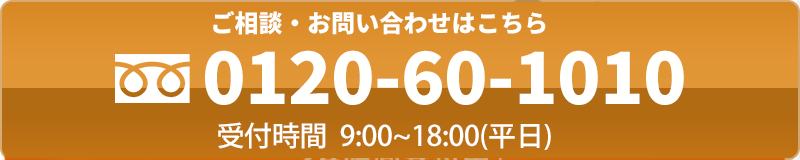
医療、介護施設の設計施工を得意とする「FULLsupport」が運営。
当サイトではクリニックにまつわる設計や内装工事にまつわる記事を随時更新中